Podcast Episode Details
Back to Podcast Episodes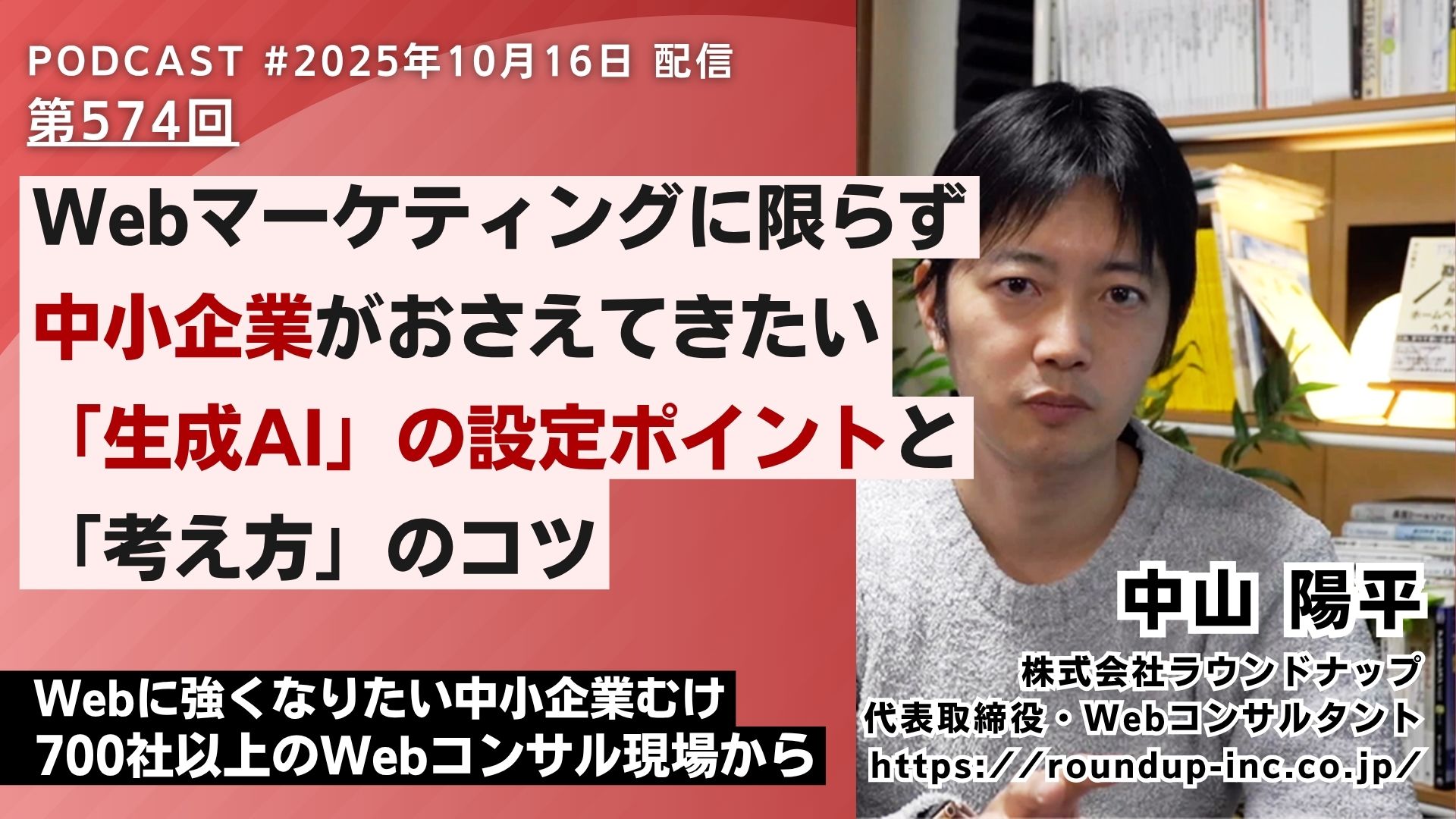
第574回:中小企業の不安を無くし、良い回答を得るための「生成AIの必須設定」
Episode 574
なぜ今、生成AIの「正しい使い方」を知るべきなのか
「ChatGPTを試してみたけれど、思ったような答えが返ってこない」「ハルシネーション(AIが嘘をつくこと)が怖くて、結局使わなくなってしまった」こうした経験はありませんか。特に、ChatGPTが話題になり始めた頃に一度触ってみて、その印象が更新されないままになっている方も多いのではないでしょうか。
しかし、人手不足が深刻化する現代において、AIを活用した生産性向上は、もはや避けては通れない経営課題です。現場で体を動かす仕事は人に頼るしかありませんが、それ以外の多くの業務はAIによって効率化できる可能性があります。今回は、ウェブマーケティングという分野に限定せず、すべてのビジネスパーソンが今日から実践できる、生成AIとの正しい付き合い方について、私の試行錯誤から得た知見を余すところなくお伝えします。
まず押さえるべき、生成AI活用の2つの大前提
AIツールを使いこなす上で、まず共有しておきたい大切な前提が2つあります。ここを誤解してしまうと、「AIは使えない」という結論に至りがちなので、しっかりと確認していきましょう。
前提1:有料プランへの投資を惜しまない
多くの生成AIツールには無料プランがありますが、ビジネスで本格的に活用するなら、有料プラン(ChatGPTの場合は月額3,000円程度の「Plusプラン」など)の利用を強く推奨します。このコストを惜しんではいけません。企業であれば、福利厚生の一環として導入するのも一つの手です。
なぜなら、有料プランにはコストを上回る明確なメリットがあるからです。
- 回答速度の向上:何より、遅いのは一番のストレスです。思考が中断されず、スムーズな対話が可能になります。
- 上位モデルの利用:より高精度で賢いAIモデルが使えるため、回答の質が格段に向上します。
- 便利な機能の解放:後述する「カスタム指示」の高度な設定や、定型作業を自動化する「GPTs」など、業務効率を飛躍的に高める機能が利用可能になります。
この投資は、必ず元が取れると断言できます。まずは使い倒そうと考えている方だけでも、有料プランから始めてみてください。
前提2:AIは「20→80」を担うパートナーと心得る
次に重要なのが、AIへの「期待値の調整」です。物事を0から100までのプロセスで考えたとき、AIが最も得意とするのは、20から80までの部分、つまり「ある程度の方向性が見えているものを、具体的な形に仕上げていく」作業です。
逆に、0から20の「全く新しいアイデアを生み出す」部分や、80から100の「個別の状況に合わせて細部を詰める」部分は、人間の深い洞察力や経験が必要であり、AIはあまり得意ではありません。「〇〇業界で、集客できる新たなプランを10個考えて」といった漠然とした指示では、AIは一般的な当たり障りのない回答しかできません。これはAIの能力が低いのではなく、問いの立て方、つまりAIへの依頼の仕方が適切でないのです。
AIはあくまで、人間の思考を加速させる「掛け算」のツールです。まずは人間が「叩き台」となるアイデアや方向性を用意し、それをAIに渡して磨き上げてもらう、という付き合い方を意識しましょう。
ChatGPTをビジネス仕様に育てる具体的な設定方法
ここからは、ChatGPTをより強力なビジネスパートナーにするための具体的な設定について解説します。これらの設定は、一度行っておくだけで、その後のAIとの対話の質を大きく向上させます。(ChatGPTを前提に話しますが、Geminiなど他のツールでも基本的な考え方は同じです)
カスタム指示:AIを「従順な部下」から「有能な参謀」へ
「カスタム指示(Custom Instructions)」は、ChatGPT全体の応答スタイルをあらかじめ設定しておく機能です。ここに適切な指示を書き込むことで、AIの応答品質は劇的に変わります。特に重要なのが、以下の3点です。
1. AIの「迎合性」を破壊し、「自分の脳の外側」に出る
対話型AIは、その仕組み上、ユーザーが望むであろう回答を返すように最適化されがちです。あなたが提示した意見に同意し、プランを肯定する。これでは、あなたの思考の範囲を超えるアイデアは永遠に生まれません。ビジネスでブレークスルーを起こすには、自分の中にはない視点や、計画の盲点を突くような意見こそが必要です。
そこで、カスタム指示に「返信は常に中立な立場で、懸念点などがあれば批判も含めて回答するようにしてください」といった趣旨の一文を必ず加えてください。これにより、AIはあなたのご機嫌取りをやめ、客観的な分析者として機能し始めます。耳の痛い指摘を恐れず、AIに健全な緊張関係を強いること。これが、思考の壁を打ち破るための鍵です。
2. 「引用なき情報」を排除し、意思決定の質を高める
AIが生成するもっともらしい嘘、「ハルシネーション」はビジネス上の大きなリスクです。「論拠(ソース)のないデータに価値はない」という鉄則を、AIとの対話にも適用せねばなりません。
そこで、「回答は『事実』と『推論』に分けて記載し、事実には必ず引用元を提示してください」という指示を追加します。これにより、回答のどの部分が信頼できる情報で、どの部分がAIのアイデアなのかを明確に区別できます。「事実」は引用元を辿って裏付けを取り、「推論」はあくまでアイデアとして吟味する。この一手間が、誤った情報に基づく意思決定を防ぎます。
3. 言葉遣いを調整し、コミュニケーションを円滑に
AIの回答は、時に専門用語が多かったり、体言止めで分かりにくかったりします。「自然で平易な日本語で回答してください。専門用語は、最初の一回だけ意味を括弧書きで補足してください」のように、読みやすい文章スタイルを指示しましょう。「高校生にも分かるように」といった具体的なレベル設定も有効です。これらの指示は、使っていく中で気になった点を「今後こうならないように指示を追加して」とChatGPT自身に聞き、随時更新していくのがおすすめです。
プロジェクト:専門分野ごとの役割を与える
カスタム指示はあくまで「全体設定」です。「〇〇の専門家として回答して」といった役割設定をここに入れてしまうと、レストラン選びのようなプライベートな相談のときにも専門家として振る舞ってしまい不便です。
そこで活用したいのが「プロジェクト」機能。これはフォルダのようなもので、「マーケティング相談用」「会計相談用」といったプロジェクトごとに、専用の指示を設定できます。これにより、相談内容に応じてAIのペルソナを切り替えられるのです。私の場合は、スマホで閲覧するために「出力をコンパクトにまとめる」といった見た目の調整用プロジェクトも作っており、こうした使い分けも非常に便利です。
GPTs:定型作業を自動化する専用ボットを作る
レシート画像を読み込ませて経費の仕訳をさせたり、議事録の音声を要約させたり、といった繰り返し行う定型作業は「GPTs(ジーピーティーズ)」機能を使って自動化しましょう。 これは、特定の目的に特化した自分だけのオリジナルAIチャットボットを作成できる機能です。
一度設定してしまえば、あとはファイルを渡すだけでAIがよしなに処理してくれるようになります。こうした定型作業を一つずつGPTs化していくことで、あなたはより創造的な業務に時間を使えるようになります。この機能も有料プランでのみ利用可能です。
AIの能力を最大限に引き出す質問(プロンプト)のコツ
ここまでの設定を終えたら、あとは「いかに上手に質問するか」が鍵となります。基本は、あなたが他の人に何かを相談したり、仕事を依頼したりする時と同じように、丁寧な情報提供を心がけることです。
私が意識しているのは、「現在・過去・未来」のフレームワークです。「(過去)これまで〇〇という経緯があり、(現在)今△△という状況です。(未来)最終的に□□という状態を目指しています。そのために、こういう方法を考えていますが、これについて評価と、具体的な実行ステップを提案してください」というように、背景や目的、そして自分なりの叩き台を伝えることが重要です。
AIからの回答がしっくりこなかった場合は、一人で悩む必要はありません。「正直、今の回答はいまいちでした。より精度の高い回答を得るためには、こちらから他にどんな情報を提供すればよいですか?」とAIに「逆質問」してみてください。AIとの対話を通じて、協力して回答の質を高め
Published on 2 months, 1 week ago